
五感に訴え掛けるマーケティングの宗教的なブランド戦略
マーティン・リンストロームによれば、ニューロ・マーケティングは科学とマーケティングの歴史的な融合をもたらした。それはこれまで支配的であったマーケティングのパラダイムを展開させることになったという。 リンストロームによると、従来のマーケティングは憶測のゲームに過ぎなかった。偶然にも成功した広告は、結果的には成功する運命にあったと言った具合に、好都合に解釈されてきた。ニューロ・マーケティング以前...
Webクローラ、スクレイピング、自然言語処理、論理学、強化学習、深層学習による人工知能のブログ。

マーティン・リンストロームによれば、ニューロ・マーケティングは科学とマーケティングの歴史的な融合をもたらした。それはこれまで支配的であったマーケティングのパラダイムを展開させることになったという。 リンストロームによると、従来のマーケティングは憶測のゲームに過ぎなかった。偶然にも成功した広告は、結果的には成功する運命にあったと言った具合に、好都合に解釈されてきた。ニューロ・マーケティング以前...
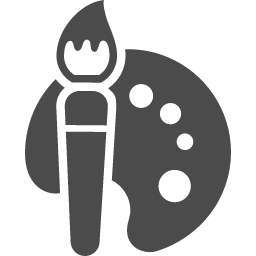
Tableau10に搭載されたクラスタ分析のアルゴリズムではK-means法が採用されている。基本的にKの個数は2~50個まで設定できるが、機能的にはKの個数を自動で決定させることもできる。この場合、Tableauは可能な限りKの個数が25になるように計算する。 Tableau uses the k-means clustering algorithm with a variance-based...
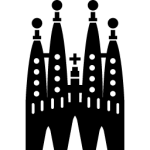
問題設定:「ゲーミフィケーション」の認識は如何にして可能になっていたのか 「ゲーミフィケーション(Gamification)」が流行り始めたのは、およそ2010年からの3,4年程度であった。「ゲーミフィケーション(Gamification)」の学問的な観察が始まったのは2012年ごろであった。それよりも比較的早期に、2010年ごろにはこの用語に注目するようになっていたマーケターたちの間では、この...
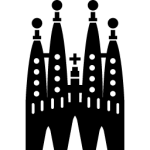
問題設定:「機械学習的には最適であっても、それがステークホルダの満足度に貢献しない」という形式の矛盾 アドテクノロジー、CRMツール、そして人工知能などといったキーワードやバズワードの影響から、深層学習や強化学習を採り入れたソフトウェア開発を要求されることは既に珍しいことではなくなっている。とりわけインターネット広告の配信部分やECサイトのレコメンドエンジンなどにおいては、KGIやKPIを定めて...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

人工知能キメラ・ネットワークに新たなキメラ・エージェント(検体番号:16770号)を追加した。Google ChromeのWebブラウザで動作する。 キメラ16770号@Web接客&アナリティクス型bot 検体番号:16770号のキメラ・エージェントは、言うなれば「Web接客bot」として、このブログに常駐しながらナビゲーションやガイダンスの役目を引き受けている。例えば各記事の...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

アメリカ統計学会の「p値」や「統計的有意性」を相対化する声明を「非」統計学的に観察するが、NAVER まとめのサイトにまとめられていた。 なのでここでは「如何にしてまとめられたのか」をまとめておこう。 「アメリカの統計学会が勧告」 私の記事は、「アメリカの統計学会が勧告」というセクションで、次の他サイトと同項目としてまとめられていた。 【統計】p<0.05時代はついに終焉か...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。
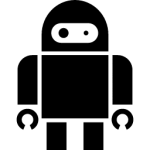
この記事の内容はAccel Brainに移動しました。
![[備忘録] アソシエーション・ルール・マイニング、アソシエーション分析、相関分析、マーケットバスケット分析と呼ばれてきたあの分析の指標(共起、信頼度、支持度、リフト)](https://media.accel-brain.com/wp-content/uploads/2016/03/arules_graph-150x150.jpg)
Q学習(Q-Learning)やバンディットアルゴリズムなどの強化学習のデモ用のコードを公開して保守していくことにした。のネタとして、共起行列上でQ学習を経路探索的に走らせて遊ぼうと思う。そこで思い当たったのがアソシエーション・ルール・マイニングであったため、重要指標をまとめておく。 二重のマイニング データマイニングの機能は、大量データの中に埋もれている有用な知識や法則を抽出することにある。...

正直Googleアナリティクスによって、自社で「ワンタグ」や「トラッキングシステム」などといった名称で呼ばれるコンバージョンのログ収集ツールを開発して保守していく必然性は既に喪失しているようにしか思えない。それはECサイトでも同様だ。 しかしGoogleアナリティクスの「拡張eコマース機能」を利用するとなると、タグの設定が複雑になる。JavaScriptのみならず、サーバサイドとの連携が必要...
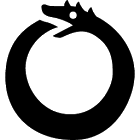
Librahack事件 Librahack氏が巻き込まれた愛知県岡崎市立図書館の公式Webサイトの事件は、クローリングやスクレイピングの仕様化と設計において、目を背けてはならない問題として知られている。 Librahack氏のプログラムとその影響 Librahack氏はこのサイトの新着図書一覧ページが使い難かったために、1秒間に1回の間隔で、1日2000回の接続を試みるプログ...
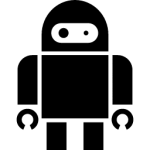
この記事の内容はAccel Brainに移動しました。